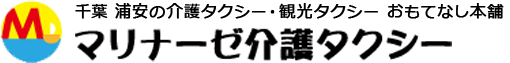船橋市
「きらきら眼鏡」池脇千鶴 久し振り“普通の女性役”に「珍しい」
中学生役で主演デビューを飾ってからおよそ20年。激しい女の情念に優しい母親の慈愛に…と、幅広く活躍している女優の池脇千鶴(36)が、9月公開の新作「きらきら眼鏡」(犬童一利(いぬどう・かずとし)監督)では、悲しみやつらさを笑顔で乗り切ろうとする複雑な役に挑んでいる。「でもすごく気持ちが伝わる台本だったので、それほど難しいというふうには思っていませんでした」と笑顔で語る。
■景色も含めて心情を撮影
「きらきら眼鏡」で演じているあかねという役は、一見するといつも明るく前向きで、悩みなどまるでないかのように思える。恋人と死別して以来、心を閉ざして生きていた若い駅員の明海(あけみ)(金井浩人)と1冊の本をきっかけに出会い、心を通わせていくが、実はあかねには余命いくばくもない恋人の裕二(安藤政信)がいた。明るさの理由は、心の中で見たものを全部輝かせる「きらきら眼鏡」をかけているからだと、明海に打ち明ける。
千葉県船橋市出身の人気作家、森沢明夫の小説を映画化したもので、撮影はすべて船橋で行った。ほとんどの場面がロングショット(遠くからの撮影)のワンカット長回しで、表情よりも全体の雰囲気で関係性を表現するという試みが印象に残る。演じる側からすると不安だったのではないかと思うが、「全くなかったですね。監督に預けられました」と言い切る。
「何とも潔いというか、顔だけをぽんぽん撮って物語を進めるのではなく、頭のてっぺんから足のつま先までのすべて、それに周りの空気、景色も含めて心情を撮ってくれる。そんな感じがしました。でも『大阪物語』のときもそうでしたからね。市川準監督も長回しでしたし、そういうのを知っていたので戸惑わなかったのかもしれません」
■台本に血が通っていれば
初めての映画出演だったその「大阪物語」(平成11年)のときにも彼女に取材している。中学生の少女の成長を描いた作品で、インタビューのときは17歳になったばかりだった。「まだ経験を積んでいないので、何が難しくて何が簡単かわかりません」と初々しい言葉を口にしていたが、それから約20年。映画にテレビに舞台にと、さまざまな役柄を演じてきた。
最近はかなり癖の強い役が多く、アジア・フィルム・アワードの助演女優賞に輝いた「そこのみにて光輝く」(26年、呉美保監督)では、夜は体を売る商売をしている貧しい暮らしの女性を熱演。今年のカンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した「万引き家族」(30年、是枝裕和監督)でも、見る者をちょっといらつかせるような嫌な役を好演している。
「役を選ぶというよりは台本ですね。いい台本がもらえたときはすごくうれしいし、血が通っているふうに書かれていれば、私はどんな役でもいい。でも気に入らないのではなく、どうしてもわからなくて、私以外の人がやった方が絶対によくなるという場合は、悔しいけど手放します。ここに自分が入るとぶちこわしてしまう、と思うときがあるんですよね」
30代半ばとなり、母親役など依頼される役柄が狭まってきたように感じることもある。
「10代のころから母親役を求められることが多かったので、年齢的に急に来たという感じではないけれど、今は私のように36歳で独身というのは当たり前ですからね。確かにこれくらいの年齢だとお母さんがしっくりくるのかもしれませんが、お母さん以外の大人の映画もいっぱい作ってくれたらいいのになって思います」
■いまだ憧れの場所
その意味で、死を間近にした恋人と影のある年下男性との間で揺れる今回のあかね役は「普通の女性が来た、というか、こういう役は珍しかったので、すごくうれしかった」と喜ぶ。
「あかねはいい大人なんだけれども、そういうところが無垢(むく)というか、男心がわかっていない。人を疑わないし、出会って仲良くなっただけで、好意を寄せられているなんて思いもしないんですよね。だから明海を知らず知らず傷つけていたんだろうなって思います」と分析する。
今後も映画の仕事が続くが、「いまだに映画は私にとって憧れの場所なので、ここに居続けたいですね」と宣言する。
「何でしょうね。ただ好きだから、ということに尽きるのかな。見るのももちろん好きですし、映画館という場所も特別なものだと思っている。それに私が子供のころから入っている現場ですからね。自分の肌に合っているんだと思います」と、また柔和な笑顔をのぞかせた。